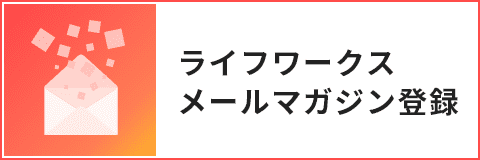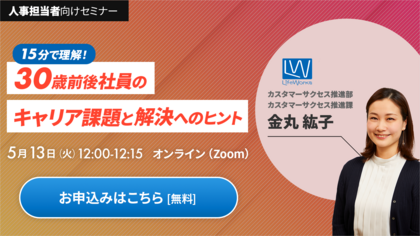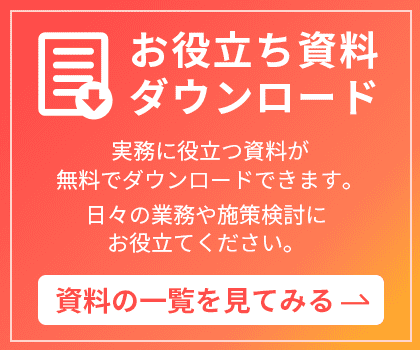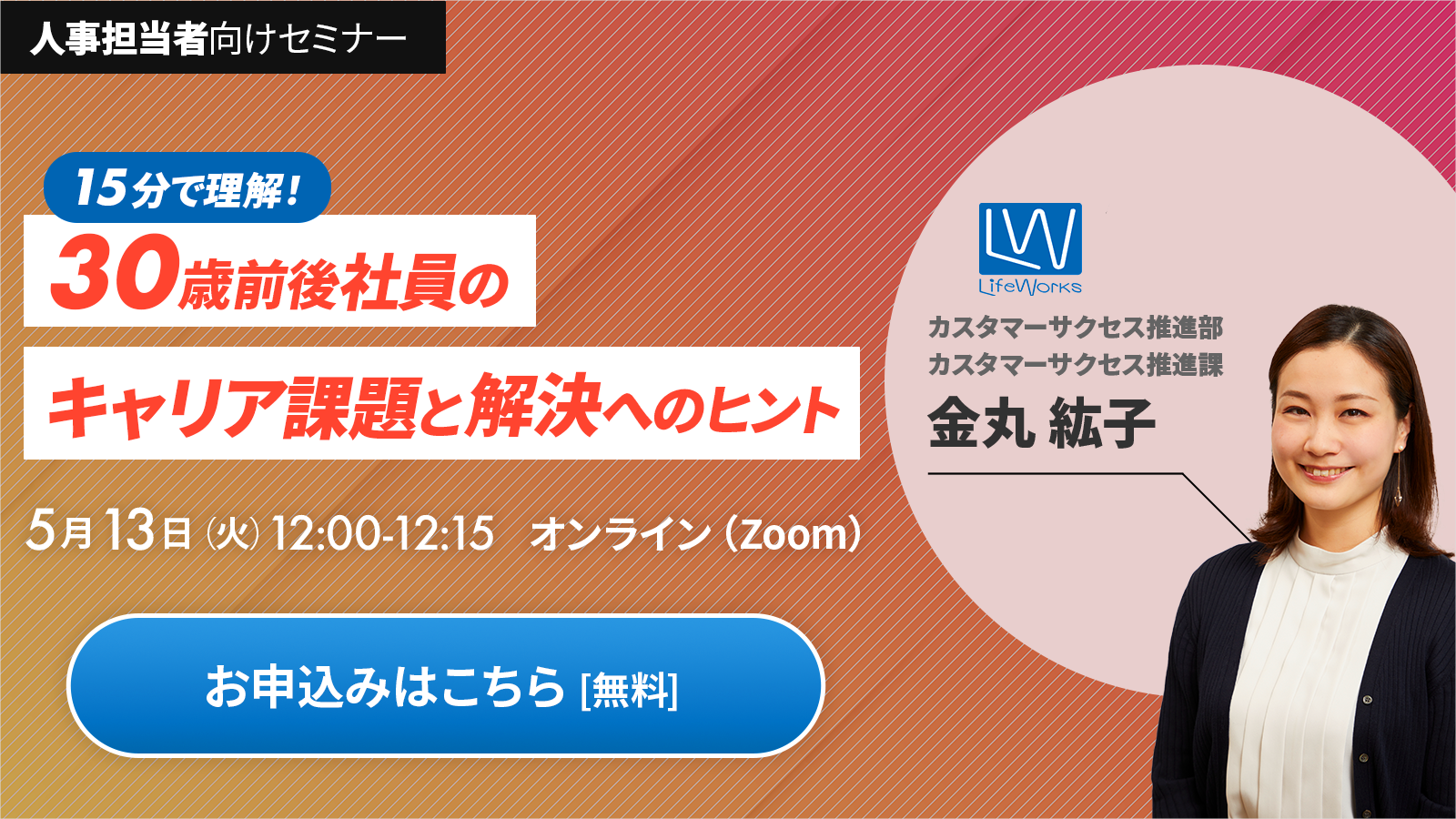社内FA制度とは?導入メリットや社内公募制度との違いを解説
人手不足が深刻な課題となっている近年では、社内FA制度に注目が集まっています。社内FA制度という言葉を耳にしたことがあっても、社内公募制度との違いや、導入にあたってのメリット・デメリットについて、正しく理解できないケースもあるかもしれません。
この記事では、社内FA制度と社内公募制度の違い、導入するメリット・デメリット、導入の際のポイントなどを解説します。

1.社内FA制度は、社員が希望する部署に自ら売り込んで異動を実現する制度
社内FA制度は、社員が希望する部署へ自らを売り込むことで、異動を実現する制度のことを指します。FAとは「free agent(フリーエージェント)」の略です。プロスポーツ界では他のチームと自由に契約を結べる権利として広く知られていますが、ビジネスの人事制度においても2000年頃から導入されはじめました。一般的に社内FA制度は、勤続年数や保有資格など、一定の基準をクリアした「FA権」を持つ社員が制度を利用できます。
従来の人事異動の多くは、企業が主導で配属先を決定しますが、社内FA制度では、社員が主体的に希望する部署への異動を表明できることが大きな特徴です。
2.社内FA制度と社内公募制度の違い
社内FA制度と混同されることが多い制度として、社内公募制度があります。社内公募制度とは、人材を求める部署が人材の要件を提示し、社内で応募を募る制度です。
社内FA制度との主な違いは、以下のとおりです。
■社内FA制度と社内公募制度の違い

社内FA制度は、社員が希望部署に対して自由に自分を売り込むことができますが、社内公募制度は希望部署が人材募集をしていないと応募ができません。また、社内FA制度の多くは、一定の基準をクリアしないと利用できないのに対し、社内公募制度は部署が提示する要件に該当する社員ならだれでも対象となります。
社内公募制度については、以下の記事をご覧ください。
社内公募制度とは?メリットや流れをわかりやすく解説
3.社内FA制度が注目される背景
社内FA制度が注目される背景には、日本の労働力不足が大きく影響しています。日本では、人口減少・少子高齢化が進行するなか、労働力の確保が深刻な課題となっており、採用活動が思うように進まない企業も少なくありません。今後も労働力人口は加速度的に減少していくとみられています。
そこで、社外からの人材獲得が難しいなら社内の人事制度を見直して人材の流動性を高めようと、社内FA制度に注目が集まっているのです。
また、人事制度の見直しの背景として、仕事に対する価値観の多様化も挙げられます。企業に自分のキャリアを委ねるのではなく、自発的にキャリアパスを形成しようとする社員が増加していることから、モチベーションの向上や社員の定着率を高めようと、社内FA制度を導入する企業が増えています。
4. 社内FA制度を導入するメリット
社内FA制度を導入するとどのようなメリットを得られるのでしょうか。代表的な導入のメリットをご紹介します。
1) キャリア自律の促進
社内FA制度を導入するメリットとして、キャリア自律の促進が挙げられます。社内FA制度を導入することで、社員が主体的に行動する人材へと育ちやすい環境整備ができます。社員に「自分を売り込めば希望する部署に異動できるかもしれない」という気づきやきっかけを与えられるでしょう。自分の努力次第で希望の部署異動が叶うならば、キャリア形成に向けて自主的に考え、行動する可能性が生まれやすくなるといえます。
2) エンゲージメント向上や離職リスクの低減
社内FA制度を導入し、社員が「キャリアパスを自ら選択できる」という実感を得られるようになれば、企業への帰属意識や満足感の向上につながりやすくなります。
従来の人事異動では、配属先が社員の希望の部署ではなかった場合、モチベーションの低下や離職のリスクがありました。しかし、社内FA制度を導入すれば、まずは社内の異動希望を出すという選択肢が出てくるため、意欲のある人材の流出予防にも寄与するでしょう。
3) 採用経費の削減
人材不足や採用手法の多様化を背景に、採用にかかるコストは増加傾向にあります。社内で人材ニーズが発生した際に、社外から人材採用を実施するのではなく、社員の異動により適材適所の人事配置ができれば、採用コストの削減につながります。
また、社内異動なら、社内の基本的なルールや制度、組織体制、システムなどを社員が理解しているため、教育コストが抑えられることもメリットです。
5.社内FA制度を導入するデメリット
社内FA制度の導入にはメリットもある一方で、デメリットも考えられます。社内FA制度を導入するデメリットを解説します。
1) 人事部門の業務負担が増える
社内FA制度を導入すると、人事部門の業務負担が増加します。社内FA制度の運用、管理方法の確立だけではなく、配置転換が発生した際の異動部署間での話し合いや欠員補充の対応、異動者へのフォローといった調整業務も必要です。
また、社内FA制度の場合は、どの社員がどのような部署に異動を希望するのかわかりません。通常の人事異動の業務に加えて、人事部門の対応は複雑化する可能性が高いといえます。
2) 人間関係のトラブルが生じる可能性がある
社内FA制度を利用して異動した場合、所属していた部署での信頼関係に影響が出るケースがあります。所属していた部署の上司やメンバーから「事前に相談してもらえなかった」「不満があるなら言ってくれればよかったのに」と思われてしまう可能性もないとはいえません。
また、社内FA制度の異動により、部署内の人員不足が生じるケースもあります。残ったメンバーに業務の負担がかかるだけでなく、他部署の社員が異動を余儀なくされたりすることもあるかもしれません。
3) 企業規模によっては難しいケースがある
社内FA制度は、人員に余裕がある大手企業向きの制度といえます。中小規模の企業の場合は、一人ひとりの担当範囲が広く、社内の人材の流動性が高まると機能不全を起こしかねません。
例えば、ひとつの部署に社員が数十名いるような企業と、1~2名しかいない企業では、異動者が発生する際の影響範囲やその度合いが異なります。
社内FA制度の導入の際は、実現可能な企業規模かどうか、デメリットよりメリットが上回るかどうかを検討することが大切です。社内FA制度の導入が難しい場合は「ジョブローテーション」を検討するのもひとつの方法です。
ジョブローテーションについては、以下の記事をご覧ください。
ジョブローテーションとは?メリットや効果を高めるポイントを解説
6.社内FA制度を導入する際のポイント
社内FA制度を導入する際はどのようなポイントを押さえておけばよいのでしょうか。主な導入時のポイントを紹介します。
1) 社員が納得する条件を設定する
社内FA制度では、利用するための一定の条件を設定します。その際に、社員が納得する条件にすることが重要です。FA権を獲得するための代表的な条件は、「勤続◯年以上」「一定以上の実績」「専門性の高い資格取得」などです。
また、不透明な運用は社員の不信感を招き、制度の信頼性が損なわれる可能性があります。採用の基準や評価のプロセスを開示するなどして、公正な評価が行われていることを社員に理解してもらうようにしましょう。
2) 個人情報の取り扱いに注意する
社内FA制度を利用した社員を社内で公表するかどうかは慎重に検討する必要があります。公表しない場合は、人事部門と部署の責任者で、社員の個人情報を厳格に取り扱うことが重要です。
万が一、社内FA制度を利用したことを所属部署の上司などに知られてしまった場合、信頼関係の悪化を招くリスクはゼロではありません。社内FA制度の運用の際は、社員の個人情報の管理を徹底しましょう。
3) 十分なフォローアップ体制を整える
社内FA制度を導入する際のポイントは、十分なフォローアップ体制を整えることです。社員が自ら希望しているとはいえ、新しい部署への異動には不安が伴うこともあります。また、異動希望が叶わなかった場合、モチベーションの低下も考えられるでしょう。
選考中は状況をタイムリーに伝え、建設的なフィードバックを提供したり、異動後の早期戦力化に向けて、異動先部署に社員とのコミュニケーションを活発化させるための働きかけを行ったりすることが重要です。
また、社内FA制度で異動者が出た部署は、引継ぎや欠員補充といった社内調整が必要になるため、社員だけではなく、部署へのフォローアップ体制も整えておくことをおすすめします。
7.社内FA制度を導入し、社員の自律的なキャリア形成を支援しよう
社内FA制度のように、社員が主体的に自分のキャリアを選択できる制度があれば、自律的なキャリア形成を育むきっかけになるでしょう。特に、自ら手を挙げて異動希望を出す社内FA制度は、自分からポジションをつかみ取りにいくため、異動後はモチベーション高く仕事に取り組みやすくなります。
また、現在の部署が自分の思い描くキャリアと異なると感じている社員は、退職を選択する前に社内FA制度の活用を考えるかもしれません。
社員の自律的なキャリア形成の支援と離職防止のためにも、社内FA制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
株式会社ライフワークスでは、社員(従業員)のキャリア支援を検討・実施する方に向けて、さまざまなソリューションを提供しています。各年代の課題に合わせた「キャリア自律研修」もそのひとつです。一人ひとりがキャリアを考えることは、スキルや知識・経験を意欲的に身に付け、成長することとも強く結びついています。人材育成を検討する際に参考になる資料も提供していますので、ぜひお問い合わせください。
キャリア自律研修については、下記のページをご覧ください。
キャリア開発 仕組・体制構築支援サービス キャリア自律研修
この記事の編集担当

黄瀬 真理
大学卒業後、システム開発に関わった後、人材業界で転職支援、企業向けキャリア開発支援などに幅広く関わる。複業、ワーケーションなど、時間や場所に捉われない働き方を自らも実践中。
国家資格キャリアコンサルタント/ プロティアン・キャリア協会広報アンバサダー / 人的資本経営リーダー認証者/ management3.0受講認定
talentbook:https://www.talent-book.jp/lifeworks/stories/49055
Twitter:https://twitter.com/RussiaRikugame
Linkedin:https://www.linkedin.com/in/marikinose/